株式会社アット、尹未宇社長 TOPから学ぶ前編

東京都、神奈川県に@!アットの屋号で3店舗を運営する株式会社アットの尹未宇社長のトップインタビューです。前編では前回のインタビューから5年が経ち、どのような変化があったのかをお伺いしました。
本日はよろしくお願いいたします。今回、3回目のトップインタビューです。 1回目は尹社長のキャリアについて、2回目は人材育成についてお話をお伺いしました。 5年後の今、変化はありましたか?
大きく変わりました。もう私がやることがほとんどなくて、新しいことに目を向けたり、今まで以上に様々なことを考える時間を作ることが出来るようになりました。
具体的にはどのような変化があったのですか?
以前はとてつもなくワンマン経営の会社でした。私が全部決めるタイプなので、トップダウンが多かったのですが、今は社員に任せる仕事が増えて、私が決めることは非常に少なくなりました。
社員の成長の結果なのですね。
社員が皆成長してくれて、今は信頼のおける社員しかいないので、とても頼もしく感じています。
尹社長がそう感じるようになったのはいつ頃からですか?
3.4年前から特段に頼もしさを感じるようになりました。最初に統括部長の意識が向上して、その影響で店長もどんどん視点が高くなりました。
例えばどのような言動で成長を感じますか?
会社のことを自分事として語るようになりました。以前よりもずっと当事者意識を持って仕事に取り組んでくれています。
以前のインタビューで言っていた、自分で自分に火をつけて成長できる『自燃型』の社員になったということですね。
そうです。今は相手の心にどう火をつけるか、燃やすことが出来るかを考え、点火型になろうと、部下の育成に奮闘しています。
情熱の火をともす、マッチの擦り方を学ぶ段階なのですね。部下の育成を通じて自分自身も成長していく役職者は多いと思います。
部下のモチベーションをどうあげるかという点に悩んでいますね。教育は良くも悪くも悩むことが大切だと思っているので、大いに悩んでほしいです。
その分、絶対に結果はついてきますから。最近は役職者がしっかりと厳しさも持ちながら部下の教育をしてくれているので、私はそれほど厳しいことを言わなくても良くなりました。昔からの社員には、尹社長は優しくなりすぎていると言われることがあるほどです(笑)
以前に社員には起業してほしいと思っていると仰っていましたが、そういった社員は増えましたか?
そうですね。先日「最近上手くいっていないので、改めて様々なお店を回ってきました」と言う社員がいたのですが、稼働など見て、売り上げについて言及したり、経営者目線の話をするようになりました。
今まで気づかなかった点にも気付いてきたりと、明らかに起業についての意識が高まっているなと感じました。
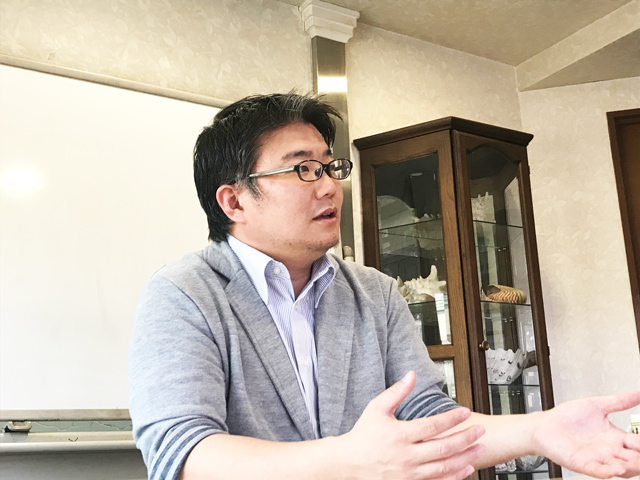
1981生まれ。アメリカ留学後、2003年父が経営する株式会社アットに入社。2007年に代表取締役就任。現在は神奈川と東京で3店舗を経営する。
近年、パチンコ業界は多くの逆風がありましたが、今はそれに加えて世界規模で猛威を振るう新型コロナウイルスの対応に追われている最中かと思います。現場の様子は変わりましたか?
今いる社員の中にはアットが悪かった時代を経験した人が少ないので、初めての挫折ではないですが、今回の新型コロナウイルスのことで気持ちが落ち込んでしまったところがありました。
しかし、アットの良さは数字ではない部分で勝負できるところにあると思っています。接客やサービス、疾病対策など含め、以前のインタビューでも中小企業の星になりたいと言いましたが、手を止めることなくソフト面で創意工夫を続けていきたいと思っています。
ソフト面を養うための研修などは定期的に行っているのですか?
やっていますね。色々な店舗を回ってリサーチしています。そこでいつも社員に言っているのは、ただ単にお店に行くだけではダメだと。その店のライバル店の店長の気持ちで見なさいと言っています。
そういう視点で見ると「この取り組みは素晴らしくて、うちの店にとっては嫌だな」とか「これは自分の店舗でもできそうだから参考にしよう」ということを感じるはずなのです。感情が動くと人は自分事として考えるようになりますから、そこは意識するようにと伝えています。
自分事としてとらえることで、より深く考えるようになるという事ですね。
そういうスタンスなので、私との研修は皆嫌がりますけどね。
嫌がるのですか?
嫌だと思いますよ。特に『後は?攻め』というのがあって、リサーチ後に社員に「見てきて何か気になることはあった?」と聞くのですが、「●●が気になりました」と答えても私が矢継ぎ早に「後は?」と繰り返すので、最初は皆怖がります。
それは私も上司にされたことがあります!
そうでしょう(笑)
ただ、怒っているわけでも、正解を求めているわけでもなく、負荷をかけることで絞り出す癖をつけてもらいたいだけなのです。そうすることで気付くことも多いですから。
社員が著しく成長した背景にはそのような研修があったからなのですね。
今はそういう感覚を持った社員ばかりになったので、とても良い状況ですし、今いる社員は皆すごく楽しそうに働いているので、そこが一番、見ていて嬉しい気持ちになりますね。

逆に、既存社員に対して、ここはもっと成長してほしいという部分はありますか?
決して悪いことではないのですが、教育の現場を見ていると指導する側の社員が、今の自分のレベルにすぐさま相手を合わせようとしてしまうことが往々にしてあるので、そこは意識して気を付けていってほしいと思います。
高いレベルの指導があっても、すぐにはついてこられない方もいるという事ですね。
私なんかは、今の役職者でも入社当初はミスをしながら成長していったのも知っているので、つい思ってしまうところがあります。ただ、大きな失敗をした人の方が伸びると思っているので、初めから出来なくてもノビシロを見てほしいなと。
自分が指導する側になると、最初から出来たような気持ちになるのは理解できます。
自分の物差しの長さというのは、見ると長くて立派には見えますが、まずは相手の物差しも把握して、共感して、あなたはこういう考え方なんですねというところから始めないと一方的になってしまうと思うのです。
それを感じた時は声をかけるのですか?
気付いたら言うようにしています。今の指導は自分の視点だけで、相手の視点に立ってないよねと、率直に。
後編に続く



